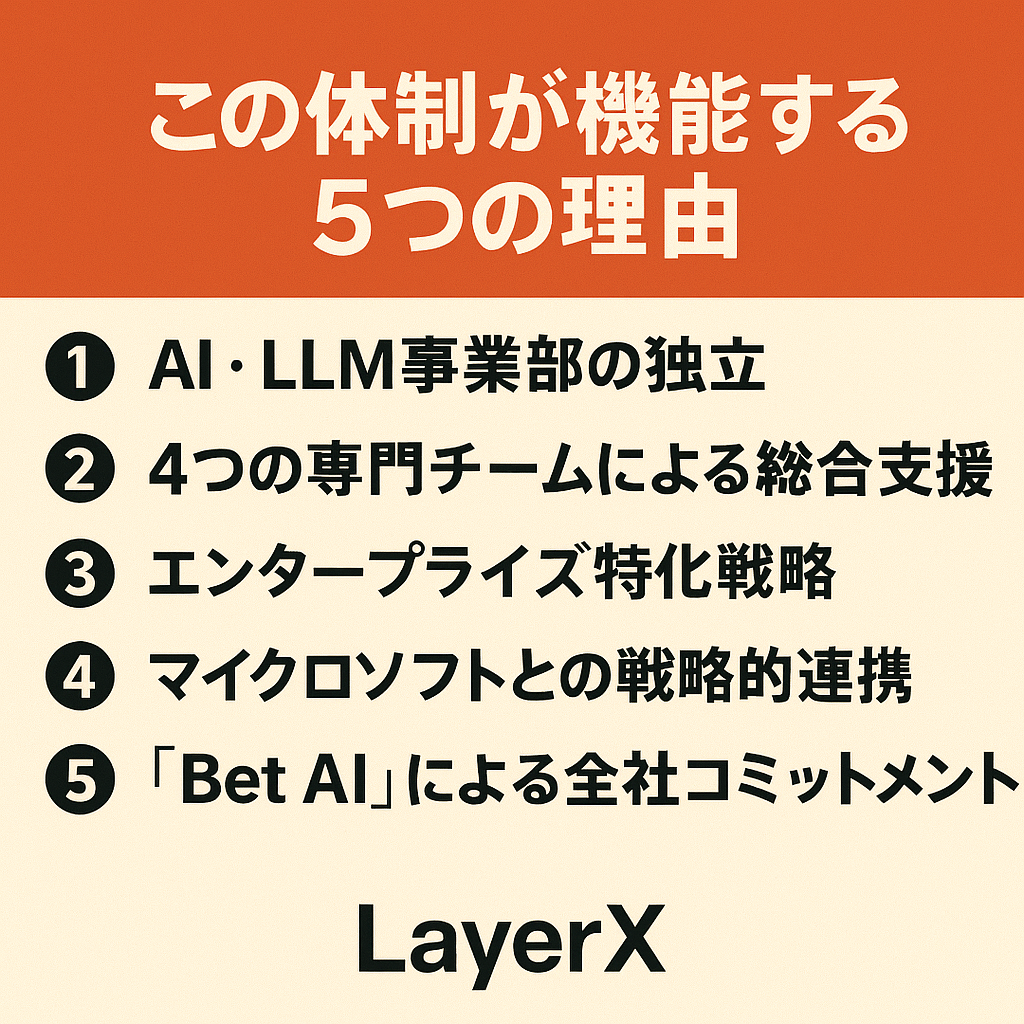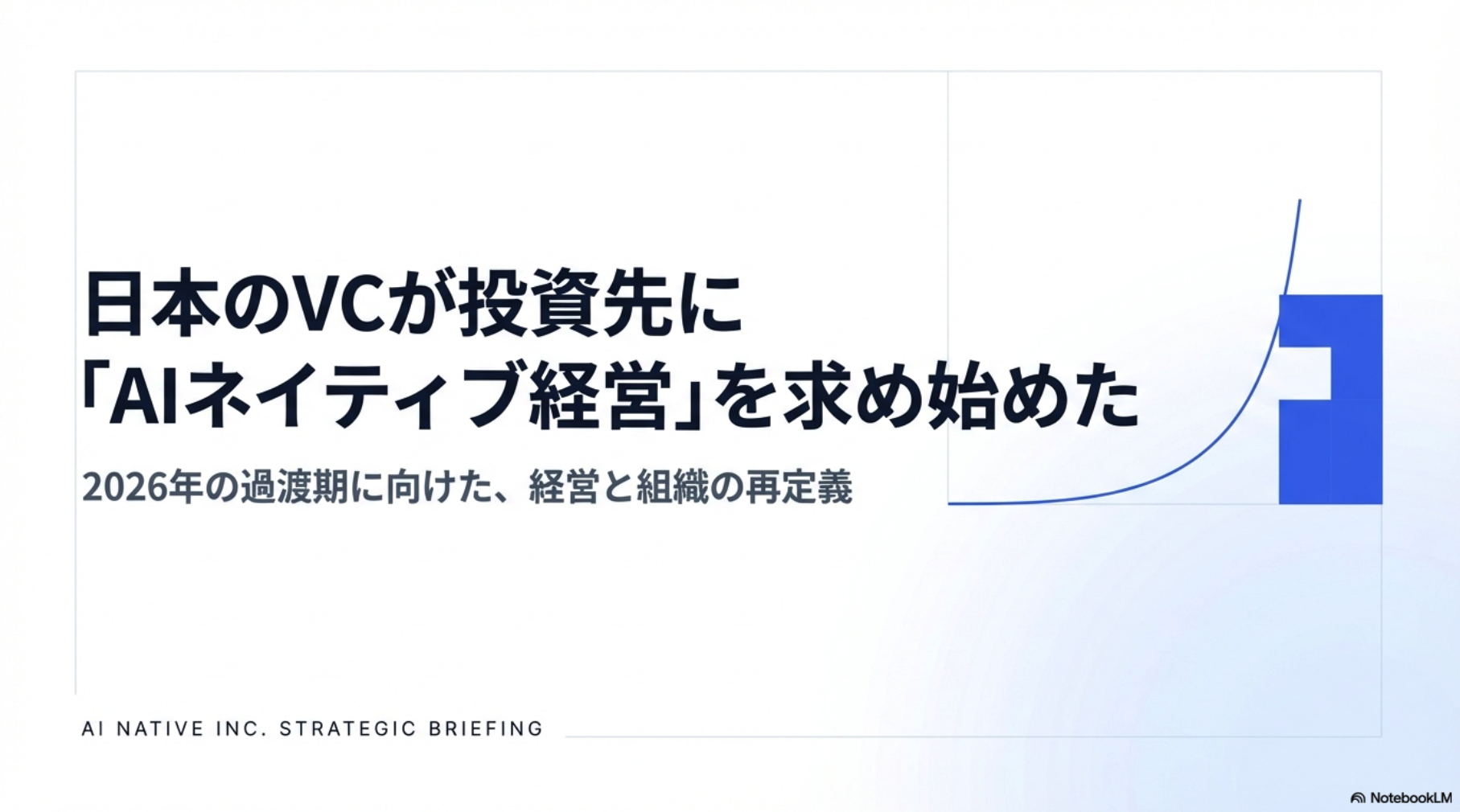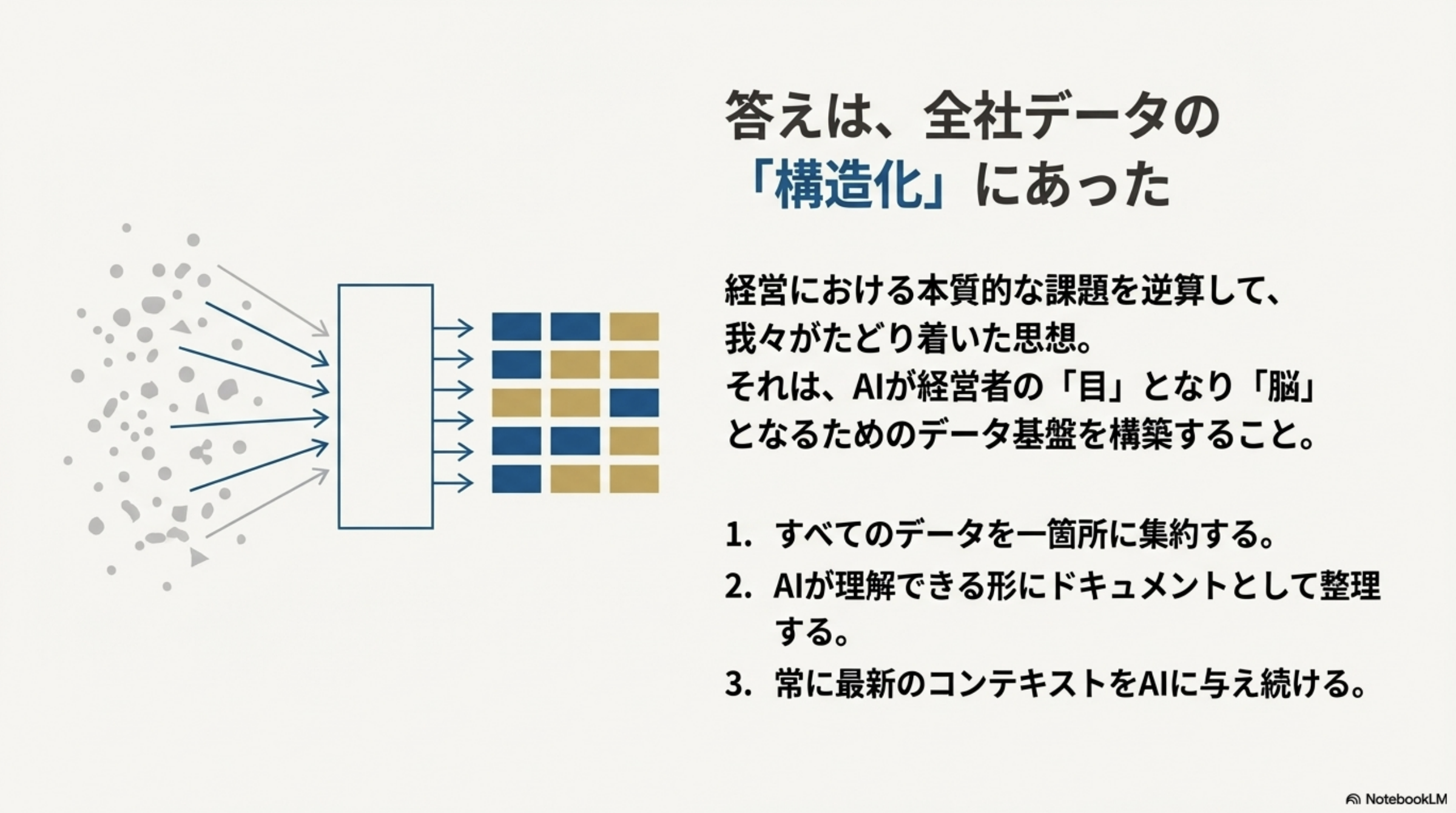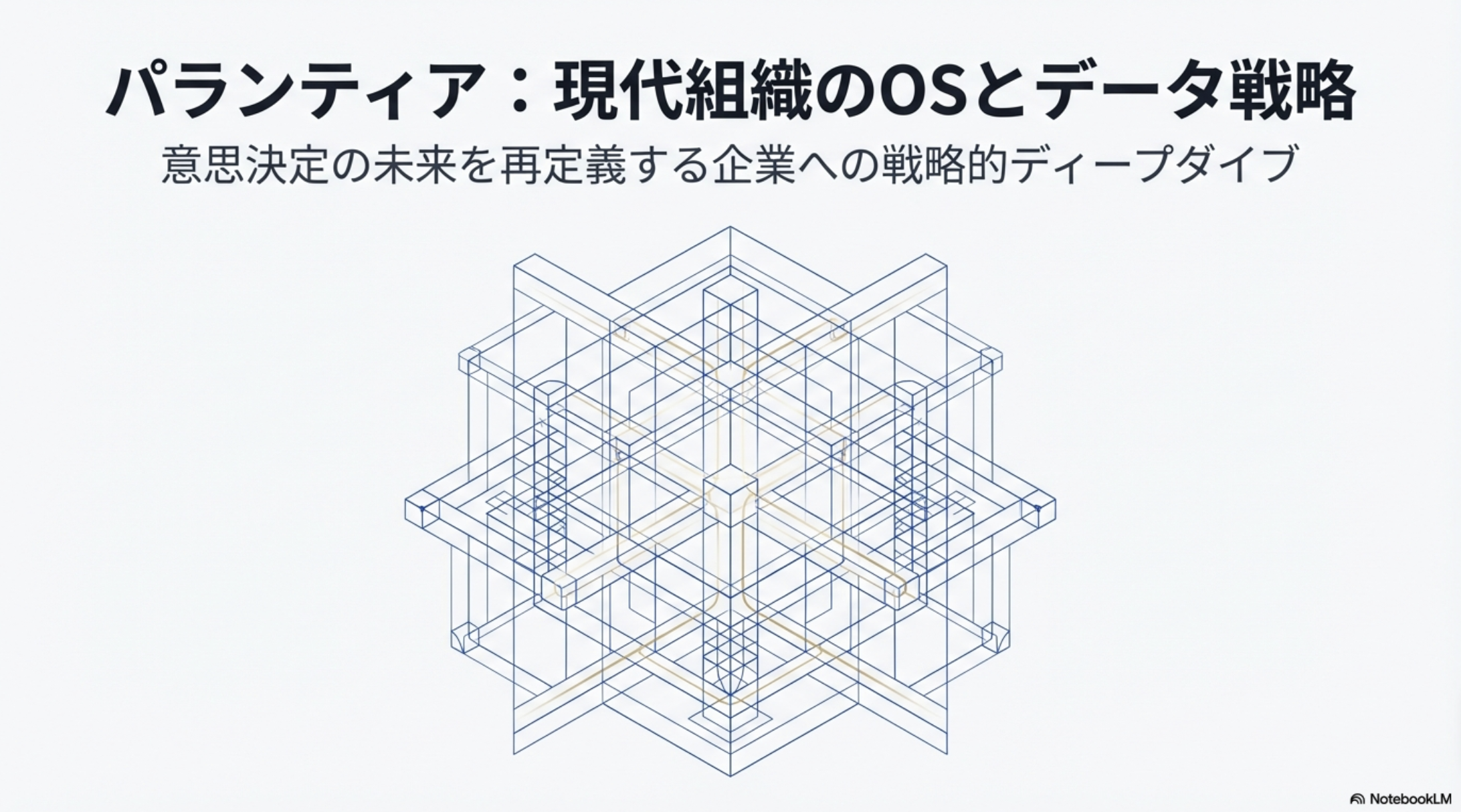📋 AI組織レビューとは
企業のAI推進体制や取り組みを分析し、他の企業にもわかりやすく伝え、AI推進を支援することを目的とした企画です。本記事は、その第5弾として、法人支出管理サービス「バクラク」と生成AIプラットフォーム「Ai Workforce」を展開するLayerXの組織体制を徹底分析しました。
この記事で伝えたいこと(結論)
LayerXのAI推進の最大の特徴は、「Bet AI」というコミットメントのもと、AI・LLM事業部を独立させたプロダクト開発体制です。2023年11月にAI・LLM事業部を設立し、2024年6月には大手企業向け生成AIプラットフォーム「Ai Workforce」をリリース。MUFG銀行や三井物産など、大企業での導入実績を積み重ねています。
本記事では、LayerXのAI推進体制を組織図から具体的な施策まで徹底分析し、他社が参考にできる実践的なポイントを抽出します。
重要: LayerXは「Bet AI」、つまり全社を挙げて生成AIに積極投資する方針を明確にしています。これが組織体制にも反映されています。
誰向けの記事か
- 経営者・役員(エンタープライズ向けAI事業を検討中)
- AI推進担当者(大企業向けAI導入支援に関心がある)
- CTO・技術責任者(LLM技術の事業化を推進したい)
- プロダクトマネージャー(エンタープライズ向けAIプロダクト開発に携わる)
本記事のポイント
- AI・LLM事業部の独立: 専門組織として事業化を推進
- エンタープライズ特化: 大企業の業務変革を支援するAi Workforce
- 複数の専門チーム編成: LLM、コンサルティング、プロダクト、BizDevの4チーム体制
- マイクロソフトとの連携: 開発・営業での戦略的パートナーシップ
- 全社的なAI活用: 内製ツール「Sales Portal」による業務効率化
次章以降で、LayerXの組織構造と具体的な施策を詳しく見ていきます。
📚 「Bet AI」戦略とエンタープライズAI事業
LayerXのような「Bet AI」戦略を掲げる企業では、経営層によるAI投資の意思決定とAI事業部の独立が鍵となります。詳しくはCAIO導入の意味と進め方|AI時代の経営戦略【経営者向け完全ガイド】をご参照ください。
LayerX企業概要とAI推進の背景
LayerXは、法人支出管理サービス「バクラク」と生成AIプラットフォーム「Ai Workforce」を展開するスタートアップ企業です(公式サイト)。「すべての経済活動をデジタル化する」というビジョンのもと、企業や行政のデジタル化を推進しています。
企業プロフィール
LayerXは、2018年8月設立のSaaS企業です(代表取締役CEO: 福島良典氏、代表取締役CTO: 松本勇気氏)。従業員数385名(2024年10月末時点)、資本金132.6億円(準備金含む)を擁し、バクラク事業とAi Workforce事業を両輪で展開しています。
AI・LLM事業を本格化した背景
LayerXがAI・LLM事業を本格化した背景には、以下のような認識があったのではないかと推測されます。
- LLM技術の成熟: 大規模言語モデルがエンタープライズ業務に実用的なレベルに到達
- 大企業の業務変革ニーズ: ドキュメントワークの効率化という明確な課題が存在
- バクラク事業での知見: 法人向けSaaSの開発・運用ノウハウを活用
- 経営層の強いコミットメント: 「Bet AI」として全社を挙げてAIに投資する方針
LayerXのAI推進組織体制
LayerXの組織は、AI・LLM事業部を独立させ、バクラク事業と並ぶ主要事業として位置付けています。AI・LLM事業部は、LLM、コンサルティング、プロダクト開発、BizDevの4つの専門チームで構成されていると考えられます。
全体構成の俯瞰図
LayerXのAI推進組織は、以下のような構造になっていると推測されます。
※ 以下は公開情報から推測し、体制を構造化したものです
LayerX
│
├─ 経営層
│ ├─ 代表取締役CEO: 福島良典氏
│ └─ 代表取締役CTO: 松本勇気氏
│
├─ バクラク事業
│ └─ 法人支出管理サービスの開発・運営
│
├─ AI・LLM事業部(2023年11月設立)
│ │
│ ├─ LLMチーム
│ │ │
│ │ ├─ 顧客業務ドメインの深い理解
│ │ │ ├─ 各企業の業務プロセス分析
│ │ │ ├─ ドキュメントワーク調査
│ │ │ └─ 課題の特定・優先順位付け
│ │ │
│ │ ├─ AIワークフローの構築
│ │ │ ├─ 業務プロセスに最適化したワークフロー設計
│ │ │ ├─ LLMプロンプトエンジニアリング
│ │ │ ├─ RAG(Retrieval-Augmented Generation)実装
│ │ │ └─ 精度検証・チューニング
│ │ │
│ │ └─ 継続的な改善
│ │ ├─ 利用データの分析
│ │ ├─ フィードバック収集
│ │ └─ モデル・ワークフローの最適化
│ │
│ ├─ コンサルティングチーム(PjMチーム)
│ │ │
│ │ ├─ 大企業向け導入コンサルティング
│ │ │ ├─ 業務ヒアリング・課題分析
│ │ │ ├─ AI活用方針の策定
│ │ │ ├─ 導入計画の立案
│ │ │ └─ 効果測定・ROI算出
│ │ │
│ │ ├─ 実装支援
│ │ │ ├─ システム導入プロジェクト管理
│ │ │ ├─ ユーザートレーニング
│ │ │ ├─ 運用体制構築支援
│ │ │ └─ トラブルシューティング
│ │ │
│ │ └─ セキュリティ・コンプライアンス対応
│ │ ├─ 企業ポリシーへの適合
│ │ ├─ データガバナンス設計
│ │ └─ 監査対応
│ │
│ ├─ プロダクト開発チーム
│ │ │
│ │ ├─ Ai Workforceプラットフォーム開発
│ │ │ ├─ コア機能開発
│ │ │ ├─ UI/UX設計・実装
│ │ │ ├─ インフラ・スケーラビリティ
│ │ │ └─ セキュリティ対策
│ │ │
│ │ ├─ 機能拡充・ユースケース開発
│ │ │ ├─ 新機能の企画・開発
│ │ │ ├─ 業界別ソリューション
│ │ │ ├─ 外部サービス連携
│ │ │ └─ カスタマイズ対応
│ │ │
│ │ └─ 品質保証・テスト
│ │ ├─ 機能テスト
│ │ ├─ パフォーマンステスト
│ │ └─ セキュリティテスト
│ │
│ └─ BizDevチーム
│ │
│ ├─ 価値創造・ユースケース開発
│ │ ├─ 市場調査・分析
│ │ ├─ 新規ユースケース発掘
│ │ ├─ パートナーシップ構築
│ │ └─ 事業化検証
│ │
│ ├─ エンタープライズセールス
│ │ ├─ 大企業向け営業活動
│ │ ├─ 提案資料作成
│ │ ├─ PoC・実証実験支援
│ │ └─ 契約交渉
│ │
│ └─ マーケティング
│ ├─ カンファレンス開催(生成AI/LLMをテーマ)
│ ├─ 事例発信
│ ├─ セミナー・ウェビナー
│ └─ コンテンツマーケティング
│
└─ 全社的なAI活用
│
├─ 内製ツール「Sales Portal」
│ ├─ 営業生産性の倍増を目指す
│ ├─ 生成AI機能の統合
│ └─ 業務効率化
│
└─ 「Bet AI」方針
├─ 顧客業務・セキュリティ要件に問題ない範囲で積極活用
├─ 社内業務プロセスへのAI組み込み
└─ AI活用文化の醸成
AI・LLM事業部の役割
2023年11月に設立されたAI・LLM事業部は、「Ai Workforce」という生成AIプラットフォームの開発・提供を通じて、大企業のドキュメントワーク効率化を支援しています。
主な特徴としては、以下のようなものが推測されます。
- エンタープライズ特化: 特定の大企業顧客に限定してサービス提供
- マイクロソフトとの連携: 開発・営業で戦略的パートナーシップを構築
- ローコード・ノーコード: 技術者でなくても業務プロセスを自動化可能
LLMチームの役割
LLMチームは、顧客の業務ドメインを深く理解し、各企業の業務プロセスに最適化したAIワークフローを構築する役割を担っています(参考: 新卒目線で見たAI・LLM事業部)。
具体的には、以下の3つの専門職種で構成されています(参考: AI・LLM事業部採用ページ)。
- リサーチエンジニア: AI/LLM技術の研究・検証、プロダクトへの技術統合
- ソフトウェアエンジニア: 大規模言語モデル製品の開発、AIワークフローの実装
- AI Solution Engineer: 企業顧客へのAIソリューション提供
チーム編成としては、少人数(数名)のチームで1つの顧客プロジェクトを担当し、以下のような業務を行っています。
- 業務プロセスの徹底的な理解: 各企業の業務フローを詳細に分析
- AIワークフロー設計: プロンプトエンジニアリング、前処理設計を含むカスタマイズワークフロー構築
- 顧客ごとの実装: 汎用的なツールではなく、企業の業務に最適化したAI処理機能を開発
- LLM出力の不確実性への対応: AIの出力精度を高めるための継続的な改善
コンサルティングチーム(PjMチーム)の役割
コンサルティングチームは、「実装コンサルタント」と「テクニカルプロジェクトマネージャー(Tech PM)」の2つの役割で、大企業が生成AI技術を活用するために必要な支援を提供しています。
実装コンサルタントは、顧客のビジネスルールや暗黙知をAI用のプロンプトや前処理に変換する役割を担います。具体的には、以下のような業務を行っています。
- 業務分析・ワークフロー設計: ドキュメント処理業務の分析、AI自動化と人間判断のバランス設計
- プロンプト設計: 顧客の業務ルールや暗黙知をAIが理解できる形に変換
- 検証性の確保: AIの出力が確認・修正しやすい設計
- 顧客・エンジニア間の調整: スムーズな実装のための橋渡し
テクニカルPMは、各企業のIT・システム構築ルールに対応しながら、スタートアップのスピード感でプロジェクトを推進します(参考: テクニカルプロジェクトマネジメント)。
- システム環境設計: マルチテナント/シングルテナント環境の設計、ネットワーク・セキュリティアーキテクチャ構築
- クラウドアーキテクチャ: 最適なクラウド構成設計、DevOps環境構築
- ステークホルダー調整: エンジニアチーム、ビジネスチーム、顧客代表者間の調整
- 企業IT規則対応: 各企業固有のIT構築ルールやコンプライアンス要件への対応
プロダクト開発チームの開発プロセス
Ai Workforceの開発は、2024年1月から本格化し、2つのスクラムチームに分けて進められています(参考: Ai Workforceの開発を支えるチーム)。
開発プロセスの特徴は以下の通りです。
- 1週間スプリント: 計画からリリースまで1週間サイクルで実施
- 役割横断的な責任: 厳密な役割分担よりもスピードを優先し、ソフトウェアエンジニアがアーキテクチャ設計からフロント/バック実装、テストまで担当
- SRE体制: 専任SREは1名のみで、他のエンジニアとSRE業務を分担
- 隔週リファクタリング日: 2週に1度、全日を使ってリファクタリング、テスト、ドキュメント整備、開発環境改善を実施
- 品質へのこだわり: チーム全体で品質を担保する文化
また、新機能開発時には、別途プロトタイプチームやR&Dチームを編成することもあります。エンタープライズ品質と仮説検証スピードの両立、最新の生成AI技術の継続的な統合が、開発における重要な課題となっています。
全社的なAI活用「Bet AI」
LayerXは、「Bet AI」という方針のもと、全社を挙げて生成AIを積極的に活用しています。顧客業務やセキュリティ要件に問題がない範囲で、社内業務にも生成AIを組み込んでいると考えられます。
具体例としては、営業チーム向けの内製ツール「Sales Portal」があり、生成AI機能を統合して営業生産性の倍増を目指しています。
具体的なAI活用施策と成果
Ai Workforceの開発・提供
2024年6月、LayerXは生成AIプラットフォーム「Ai Workforce」をリリースしました。エンタープライズ企業のドキュメントワークを効率化するローコード・ノーコードソリューションで、以下のような特徴があります。
- 大企業での導入実績: MUFG銀行、三井物産など
- マイクロソフトとの連携: Azureベースでの開発・営業協力
- 業務プロセスへの統合: 既存の業務フローにAIを組み込み
4つの専門チームによる支援体制
LayerXは、LLM、コンサルティング、プロダクト開発、BizDevの4つの専門チームにより、大企業の生成AI活用を多面的に支援しています。
- LLMチーム: 業務に最適化したワークフロー構築
- コンサルティングチーム: 導入支援とプロジェクト管理
- プロダクト開発チーム: プラットフォームの機能拡充
- BizDevチーム: 価値創造とユースケース開発
内製ツールによる社内業務効率化
「Sales Portal」など、社内向けのAIツールを開発し、営業生産性の倍増を目指しています。これにより、自社でも生成AIの効果を実証していると考えられます。
カンファレンス・イベント開催
LayerXは、「生成AI/LLM」をテーマとした大企業向けカンファレンスを開催するなど、市場啓蒙活動にも積極的に取り組んでいます。
この体制が機能する5つの理由
LayerXのAI推進体制がうまく機能している背景には、5つの成功要因があると考えられます。
1. AI・LLM事業部の独立
専門組織として独立させることで、エンタープライズ向けAI事業に集中できる体制を整えている点が成功要因と考えられます。
2. 4つの専門チームによる総合支援
技術、コンサルティング、プロダクト、ビジネス開発の4つの専門チームにより、大企業の複雑なニーズに対応できていると推測されます。
3. エンタープライズ特化戦略
大企業に絞ってサービスを提供することで、高いセキュリティ・コンプライアンス要件に対応し、深い業務理解を実現していると考えられます。
4. マイクロソフトとの戦略的連携
グローバル企業との連携により、技術面・営業面での強力なサポートを得ていると推測されます。
5. 「Bet AI」による全社コミットメント
経営層が「Bet AI」を掲げることで、全社を挙げてAIに投資する姿勢が明確になっており、組織全体の推進力になっていると考えられます。
他社への示唆
LayerXの事例から、以下のような示唆が得られます。
エンタープライズ向けAI事業のポイント
- 専門組織の独立: AI事業を独立した事業部として推進
- 4つの専門チーム編成: 技術・コンサル・プロダクト・BizDevの総合支援
- エンタープライズ特化: 大企業の要件に特化してサービス設計
- 戦略的パートナーシップ: グローバル企業との連携による信頼性向上
- 全社的なコミットメント: 「Bet AI」など明確な方針の提示
- 自社での実践: 内製ツールで効果を実証
事業立ち上げプロセスの参考
- フェーズ1: バクラク事業での法人向けSaaSノウハウ蓄積
- フェーズ2: AI・LLM事業部の設立(2023年11月)
- フェーズ3: Ai Workforceのリリース(2024年6月)
- フェーズ4: 大企業への導入拡大(MUFG、三井物産など)
- フェーズ5: マイクロソフトとの連携強化
まとめ
LayerXのAI推進体制は、AI・LLM事業部を独立させ、LLM、コンサルティング、プロダクト開発、BizDevの4つの専門チームで大企業の生成AI活用を支援する体制が特徴です。「Bet AI」という明確な方針のもと、全社を挙げて生成AIに投資しています。
エンタープライズ特化戦略により、MUFG銀行や三井物産など大企業での導入実績を積み重ね、マイクロソフトとの戦略的連携により、技術面・営業面での強力なサポートを得ていると考えられます。
他社がこの事例から学べることは、AI事業の独立、4つの専門チーム編成、エンタープライズ特化、戦略的パートナーシップ、そして全社的なコミットメントという、エンタープライズ向けAI事業の5つの柱です。