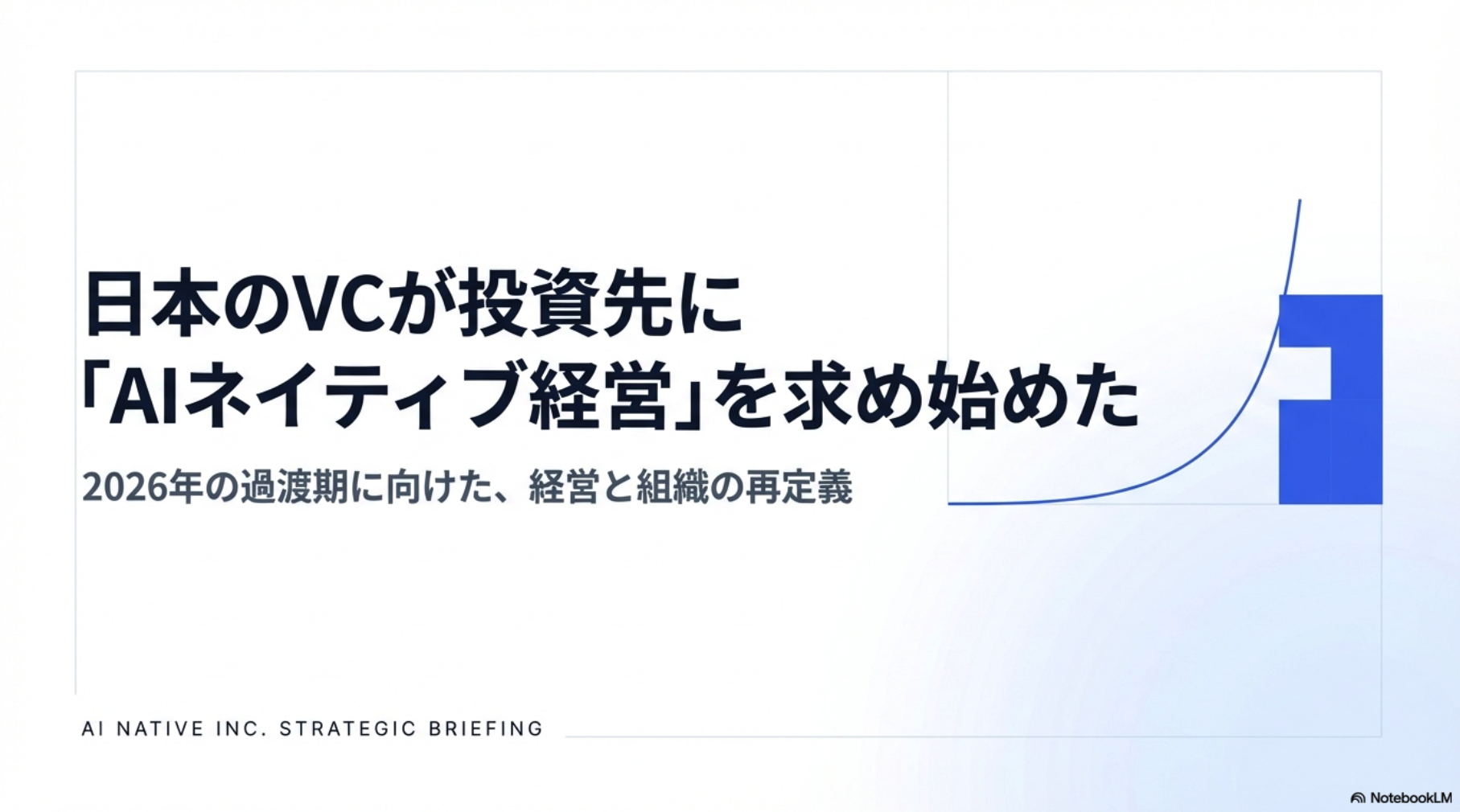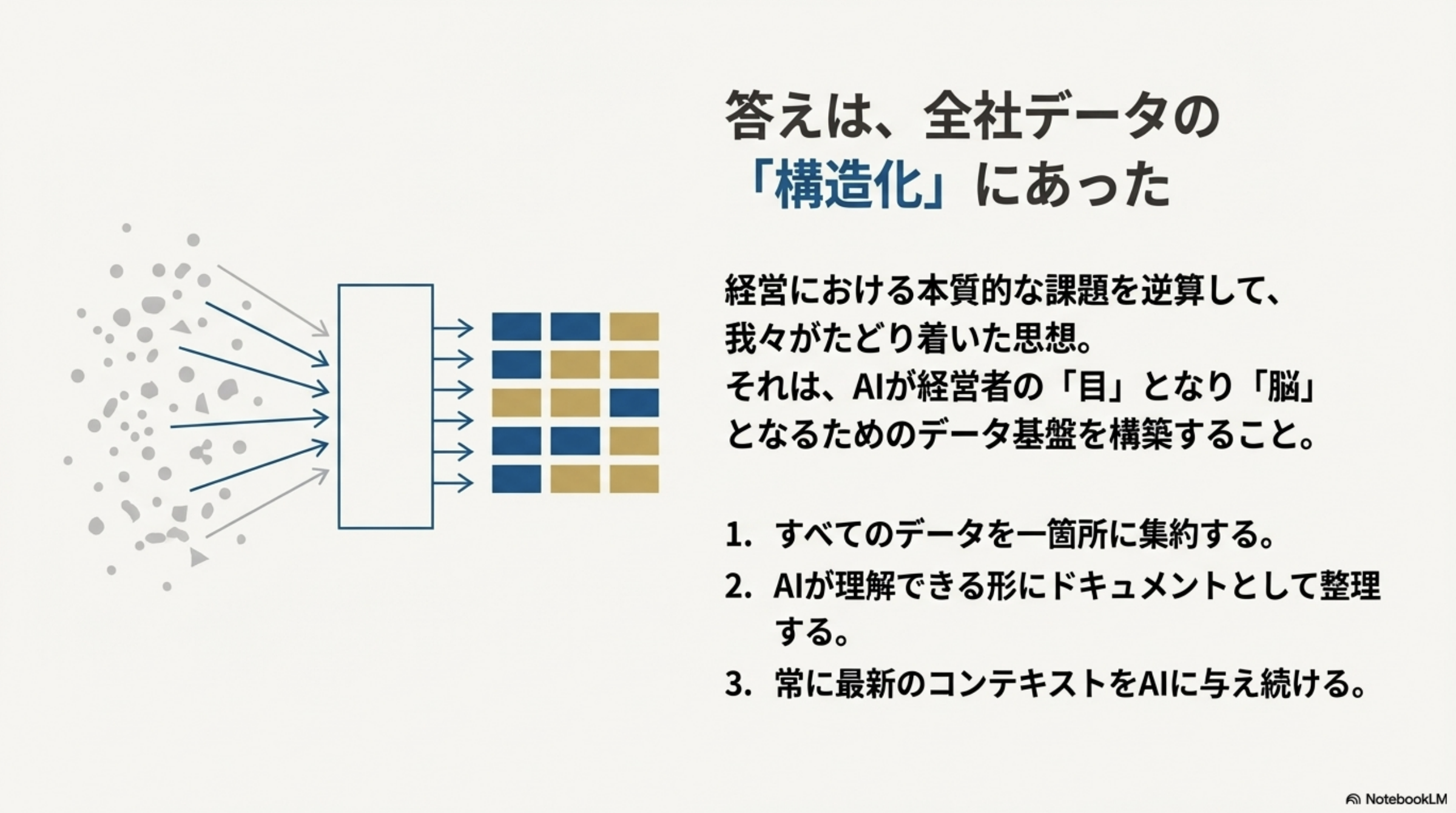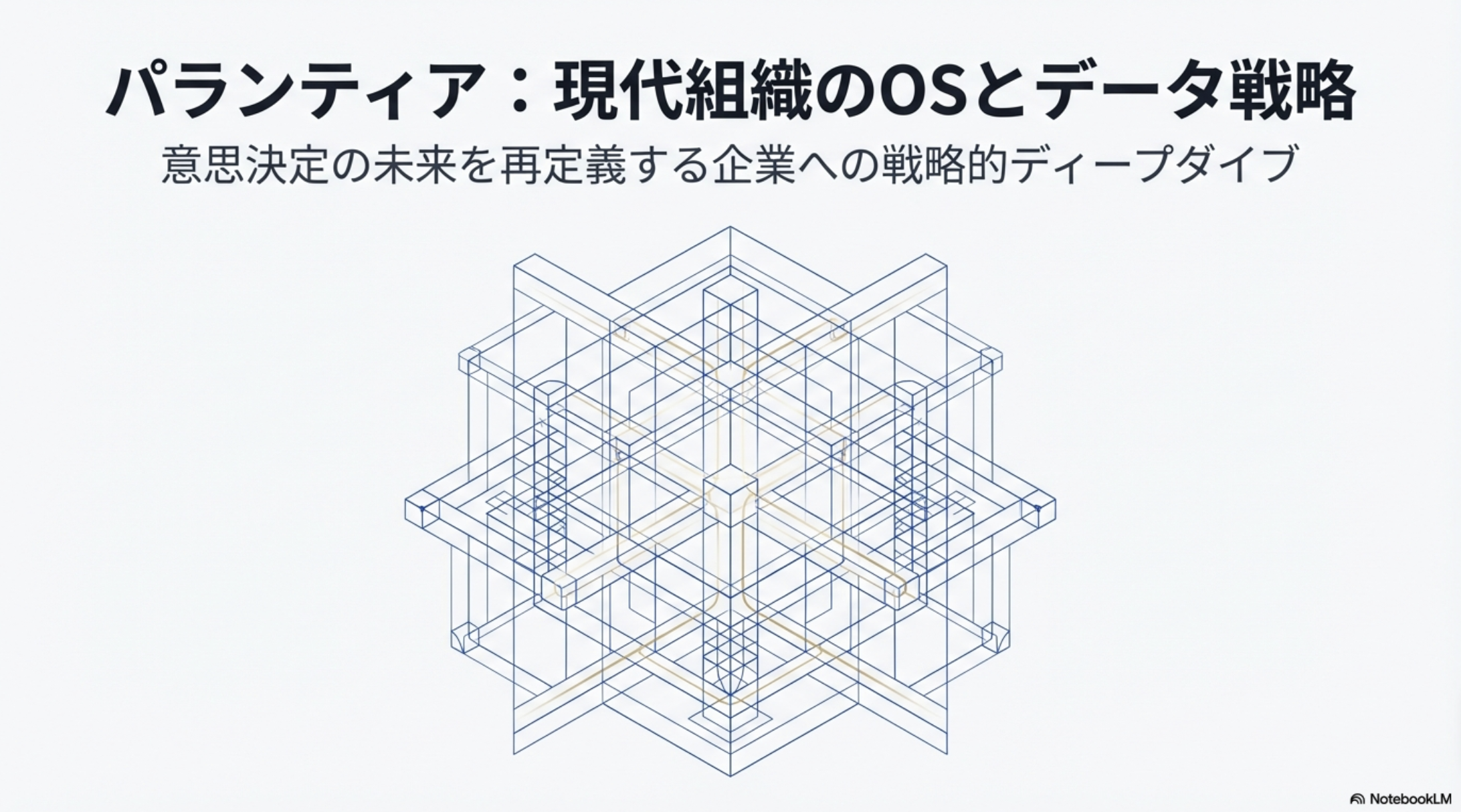⚠️ 導入初期の重要な警告
AI推進の初期段階で起きやすい問題を理解し、事前に対策を打つことが成功への鍵となります。
はじめに:AI業務効率化推進フェーズ1の現実
本記事は、AI NativeがAI顧問として実際に支援しているお客様の事例に基づいています。現在、多くの企業でAI推進が進み、各ポジションがAIツールを用いて業務効率化に取り組んでいます。特に、ビジネス職でもGASやDifyが自律的に使われ始めています。
しかし、運用できない・リリース前に詰まってしまうこともしばしば。お客様事例をもとに、改善の方法と進め方についてご紹介します。
そもそもAI業務効率化推進フェーズ1とは?
まず、本記事で扱う「フェーズ1」について簡単に整理しておきます。AI導入は一般的に段階的なアプローチで進められ、フェーズ1は基盤整備期として位置づけられています。
このフェーズ1は「実験と学習」の期間とも言えます。しかし、まさにこの時期に多くの企業が「落とし穴」にはまってしまいます。以下、実際の事例を通じて、どのような問題が発生し、どう解決すべきかを見ていきましょう。
誰向けの記事か
- 経営者:AI投資の効果を最大化したい方
- 事業責任者:部門でのAI活用を推進している方
- AI推進担当の責任者:全社的なAI導入を統括している方
- AIツールを活用してビジネスワークフローを作りたい/作られている方
お伝えしたいこと
✅ 重要なポイント
- 現場がAIツールで素早く作るのは良いが、全社としての統制が不可欠です
- 情報セキュリティ、メンテナンスコスト、ビジネススピードの観点から設計しましょう
- フェーズ1の段階で「最小統制+設計と運用の型」を先に敷くことが重要
AI業務効率化推進フェーズ1で起きる5つの落とし穴
以下では、実際の支援事例をもとに、どんな課題が生じ、どのように解決したかを具体的に示します。なお、実務ではミーティングを重ね、課題と目的、ビジネス上のタイムラインを言語化しながら合意形成していきます。
🚨 よくある"落とし穴"
1. ツール乱立
部署ごとに異なるSaaSや拡張を使用し、資産が分散して横展開や共通運用に支障が出ます。出来上がる想定イメージをシステム構成図などでもいいのでペラ1作成しておくことがおすすめです。
2. 権限/監査の欠落
誰が何を実行し、どのデータに触れたか追えず、監査や是正の再現性がありません。
3. 属人化
作った人以外が変更できず、拡張時のスピードが落ちます。ドキュメントや設定の標準がありません。急にエンジニア・PMのアサインが必要になり、ビジネス職で完結していたオペレーションにリソースやコストが必要になってきます。
4. エラー時の手詰まり
リトライや代替経路、通知がなく、停止状態が長引きます。
5. 指標不在
成功率・処理時間・例外承認の滞留時間などのKPIが未定義で、改善ループが回りません。
これらは単独で発生するというより、同時多発的に起きて相互に悪影響を及ぼすのが厄介です。例えば、権限/監査の欠落があると不具合の特定に時間がかかり、属人化と相まって復旧までのリードタイムが伸びます。結果として、現場は一層"手当て的な"改修に流れ、さらに設計負債が積み上がるという悪循環に陥ります。
AIオペレーションマネージャーという新しい潮流
こうした背景から、それらを解決するポジションとして海外や国内企業の一部でAIオペレーションマネージャーという職種が生まれてきています。
🌍 グローバルでの採用動向
米国では、OpenAI、Amazon(AWS)、NVIDIA、Scale AI、Anthropicなどの大手テック企業がAIオペレーション関連のポジションを積極的に採用。AI Systems ManagerやAI Operations Leadといった役職で、AIシステムの統合・運用管理・最適化を担う人材を求めています。

「AIオペレーションマネージャー」
— Taro Fukuyama (@taro_f) March 21, 2025
アメリカの投資先で採用しているスタートアップがいくつかあり、これから日本でも増えていくのではないか?と予想しているポジションです。… pic.twitter.com/p0Sk2IcAI8
日本でも2024年以降、ログラス、TSUIDE、Ubie、SmartHR、ユーティルなどの先進企業がAIオペレーションマネージャーのポジションを新設。「AIを前提とした業務の根本的な再設計」をリードする役割として注目を集めています。
📊 市場データ:日本のIT人材は2025年までに22万〜37万人不足すると予測され、特にAI・クラウド分野での需要が急増。2030年までには約80万人の技術専門家が必要とされています。この人材不足に対応するため、伴走型AI研修による社内人材の育成が重要な選択肢となっています。
AI Nativeでは、いくつかの企業でAIオペレーションマネージャー・開発者として参画させていただいており、単にツールを導入するだけでなく、組織全体の業務プロセスを見直し、AIを活用した持続可能な運用体制を構築しています。ここからは、その実際の事例を共有したいと思います。
AI業務効率化での課題と解決策の事例

以下では、実際に支援した企業での具体的な事例を2つご紹介します。どちらもビジネス職の方が自らAIツールを活用してオペレーションを構築したケースで、課題と解決策をまとめました。
ケース1:GAS+スプレッドシート+AIツールで作られたオペレーション
ビジネスチームでは、非常によくあるオペレーションだと思います。しかし、同時に、問題を引き起こしやすいオペレーションでもあります。具体例をご紹介していきます。
📋 ご相談のタイミング
GAS+スプレッドシート+AIツールで立ち上げたものの、柔軟性・拡張性が不足し、作成者以外がメンテナンスできない状態でした。
🔍 前提・課題
- 複雑な処理の実装困難 - GASで高度な機能を実装しようとすると、かえって運用コストが増大。事前の工数見積もりも困難
- 改善・拡張の難しさ - 作成者本人でも、後から機能改善や修正をしようとすると急激に難易度が上がる。本人がAIでの開発が初めてで理解せず開発しており、複雑な要件に耐える追加実装が困難
- フロントエンドとの連携の複雑化 - v0等のAIツールでUIを生成し、スプレッドシートのデータと連携させる構成を採用
- スケール時の管理負荷 - ページ数が増えると、スプレッドシートIDの管理、ページ生成、ルーティング設定など、管理項目が急増
- アーキテクチャの限界 - GASとスプレッドシートの組み合わせが複雑化した段階で、軽量な管理画面への移行が必要になる状況
✨ 改善したこと
- SPA構成のルーティングを再設計
- ハードコードを撤廃し、自動取得・汎用化の方針へ変更
- 設定値の外出し(環境/スプレッドシート/管理画面)と、変更手順のドキュメント化
- ログ/エラーの可視化を導入
- 最小の管理画面を用意し、設定変更や再実行を"作った人以外"でも行える運用へ移行
📄 成果物:ルーティング仕様、設定一覧(データ取得/表示/権限)、運用手順(再実行/復旧)をドキュメント化
ケース2:Difyで作られたオペレーション
📋 ご相談のタイミング
並列処理、外部サービスのAPIコールしている場面が複数あり、エラーハンドリングがないためにワークフローのどこを直せばいいのかわからない状態でした。
🔍 前提・課題
- Difyで複雑に作られていたマーケティングの記事制作オペレーション
- AI推進メンバーで、開発バックグラウンドがない方が作成していた。2ヶ月前など短期でアサインされ、高速にキャッチアップされていたが、ご担当者様が1人で改善されている状況
- マーケティングチームメンバーを含めて、開発バックグラウンドがない状態
- その中で、なかなかDifyのワークフローが成功せず、成功確率は10%程度
- ワークフロー改善のしづらさもあり、記事品質が恒常的に改善しづらい状況になっていた
💡 データ品質の重要性
AI業務効率化において、データ品質とフォーマット統一は成功の前提条件です。詳しくはAI業務効率化の前提条件:データ整理とフォーマット統一が成功の鍵をご参照ください。
✨ 改善したこと
- 元々複雑ではあるが素晴らしいワークフローが作られていたので、ワークフローのコアを残し、構成をシンプルに再設計
- 変数・プロンプト・外部API設定の命名規則とレビュー基準を策定
- エラー率をほぼ0%まで抑制し、同一工数で記事制作本数を2倍以上に拡大
📄 成果物:失敗時のフローチャート、ログの見方、再実行・別経路実行の手順書、命名規則ガイドを整備
AI Nativeのアプローチ
総合的に考えた、AIツールを活用したオペレーション設計ができるかどうかは重要になってきています。弊社では、AIオペレーションマネージャーとして外部から参画し、課題を現場にレクチャーしながら整えていくというのをハンズオンのAI顧問として行っています。経営、開発、PMを長年経験したメンバーだからこそ、そこを担えるのでぜひお問い合わせください。
回避フレーム(最小実装パッケージ)
🛡️ 最小限必要な統制項目
1. ツール/モデルの管理
ホワイトリストと、例外申請フローを明文化
2. データ分類と取扱ルール
公開/社内/秘/特秘の分類と、貼付可否、マスキング、持ち出し制限を定義
3. 承認フローの設計
誰が、どの操作を、どの閾値で承認するかを設計
4. 監査ログ
入出力・ツール実行・権限変更と保全期間を定義
5. 設計と運用の型
設定化/パラメータ化、ログ・アラート、テスト観点、フォールバック戦略、ドキュメントを整備
実装チェックリスト(30/90日)
📅 最初の30日
- ✅ 許可ツール/モデルの作成と周知、例外申請の導線を作る
- ✅ データ分類と取扱ルールを1枚に集約、貼付NG例の周知(秘密情報/PIIの例示)
- ✅ 承認フローの定義(高リスク操作のみ二段階)
- ✅ 監査ログの記録開始(少なくとも入出力/ツール実行)
情報システム部・開発組織・ビジネス組織などのステークホルダーにまとめたドキュメントを共有し、全社的な理解と協力を得るようにしましょう。
📅 60–90日
- ✅ 設定/パラメータの外出しと命名規則の統一、最小の設計ドキュメント整備
- ✅ ログ/エラー標準化、失敗時の自動通知・再実行・切替(フォールバック)
- ✅ CIの自動チェック(Lint/依存脆弱性/基本テスト)
- ✅ KPI設定(成功率、平均処理時間、例外承認のリードタイム、再実行率)とダッシュボード化
KPI/モニタリング(初期の目安)
📊 目標指標
関連記事
📚 フェーズ1関連の詳細記事
まとめ
AI推進をし始めたら、それがいかに使われる状態になるか、誰でも使えるか、セキュリティとして問題ないかなど総合的に考えて進める必要があります。
企業としてそれを使い続けていいのか、エンジニアに力を貸してもらわないとメンテナンスできないのか、その考慮がなされないまま、AIツールで適当に作っていくと柔軟性やセキュリティの問題などが発生し、取り返しのつかないことになることもあります。
🎯 成功への最短経路
フェーズ1で"最小統制+設計の型"を整え、30/90日のチェックリストで段階的に標準化することが、速度と安全性の両立への最短経路です。
特に、設定の外出し(誰でも安全に変えられる)、ログ/監査の一元化(すぐに原因に当たれる)、失敗時の手当ての型(再実行・切替・エスカレーション)は、初期段階から入れておくほど後工程が楽になります。
💡 次のアクション
AI推進でお困りの場合は、AI NativeのAI顧問サービスをご検討ください。経営・開発・PMの経験豊富なメンバーが、貴社の状況に合わせた具体的な解決策をご提案します。
お問い合わせはこちら